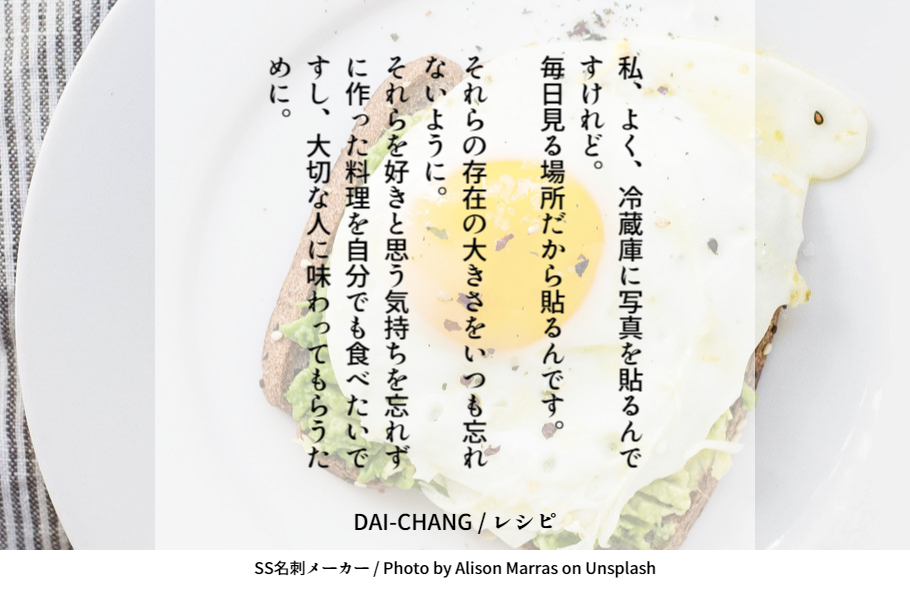
すぐに返事をするとあまりきちんと考えていないように思われそうなので、少し間をおいてみました。
でも、そのうちに、何を聞かれていたのか、“それ”が私に何を聞いてきたのか、そもそも言葉らしきものを発したのかどうかも怪しく思われてきました。
“それ”は、私がいつものようにノブオをアパートのドアの外まで見送り、吐く息もすっかり白くなったと思いながらドアの鍵をかけ部屋の方へ振り向いた時にはそこにいました。
先日、少しだけお話した“それ”です。
2本足で立つ“それ”は全身半透明で、ぶるんとしたおなか、少し小さめのぷっくりした手足、頭の上にのった小さな 2つの耳はやや尖っていて、顔はあるようにもないようにも見えましたが、鼻と思われる部分は少しだけ突き出ていました。体毛らしきものは見えません。しかし、短いしっぽがついていたので動物のようでもありました。
真夜中、突然、自分とノブオ以外の何者かが部屋に存在していたという状況に、私は非常にとまどい身動きがとれなくなりました。
裸足にサンダル履きでの玄関先は、タイルの冷たさが直に這い上がってきて私の全身を絡めとります。
“それ”を見ている両目と、冷たさを通り越し逆に熱くなってゆく足先に意識が集中されだんだんとぼうっとしてきました。
得体の知れない何者かが部屋にいるという状況を知らせたらノブオは飛ぶように戻ってきてくれるのではないかという考えもよぎりましたが、さっき部屋を出たばかりで移動中の彼が携帯電話が鳴っていることに気づく可能性の低さに思い当たったので(彼の携帯電話はいつもバイブレーションに設定されています)、他にこの状況を説明したところでよいアドバイスをくれそうな友人を思い浮かべてみました。
しかし、その誰もが彼と私が会う時間帯には既に就寝していることは想像に難くはなく、そうこう考えているうちに逆にこの何者かが、本当に何者なのかを確かめてみた方がよいのではないかと思い始めました。
見たところ、こちらに襲いかかってくるようなあぶない気配はありません。
声をかけたら鳴き声で返してくれそうな気もしてきました。
“それ”はただただそこに存在し、その存在の無機質な静けさがさっきまでおおいにとまどい波だっていた私の気持ちをなだめてくれているようでした。
さざ波の立つ海の表面ではなく、圧倒的な静けさのある深海へと潜っていくような気分でした。
楽観的すぎてお恥ずかしい話ですが私の中では、いつも仕事があるからと少しの時間を過ごすのみで部屋を後にするノブオの不在を埋めてくれる存在を見出したような、
安心に近い感情が芽生えていたのかもしれません。
とは言え、初対面の“それ”にどう声をかけてよいものかもわからずしばらく無言の時をやり過ごしました。
私、無言・・・
“それ”、無言(もしくは無音)・・・
私、無言・・・
ふいに“それ”は踵を返し、とぷとぷと歩行したかと思うと冷蔵庫を開け中へ入って行きました。
「どっこいしょ」という声が聞こえてきそうな力の入れ具合で片足ずつ、そしてするりと全身を滑り込ませてしまったので私はその行為を止めることもできませんでした。
硬直していた私の両足がその驚きで解凍したように自由を取り戻したので急いで部屋にあがり、半分開いたままの冷蔵庫のドアから覗いてみると“それ”は早くも寝息を
たて始めていました。
仕方なくしばらく観察するにとどめ、翌日には仕事もあったので自分のベッドへと戻りました。
きっと今のこの状態が自分自身が見ている夢であると思ったからです。
けれども“それ”は時々姿を現すようになりました。
ノブオが来る来ないに関わらず、ふと気がつけばぼんやりと現れ、やがて冷蔵庫の中へ入って行きます。
真夜中、部屋の明かりはなく、存在しているのは半開きのドアからもれる冷蔵庫の光と、ウィーンというモーター音、掛け布団にくるまり冷蔵庫の中の“それ”を眺める私と、冷蔵庫の中から私を眺める“それ”のみです。
お互いを見つめ合うだけの関係はまるで合わせ鏡の中の自分を眺めるようでした。
私はその場所でお酒を飲む日もありましたし、本を読みながらそのまま眠ってしまう日もありました。
“それ”については誰にも話しませんでした。
おそらく誰も知らないであろう“それ”を、私だけが知っているということに少しだけ優越感に近いものを感じていたのは確かですが、それ以上に“それ”をそっとしておきたいという気持ちの方が大きかったのです。
その日も真夜中に“それ”が現れ、いつものようにただお互いを眺める時間を過ごしていました。
「腹減った〜」
唐突に聞こえてきた声に私は我が耳を疑いました。
「腹減った〜」
明らかに声は“それ”から発せられていました。
驚くと同時に、私の部屋に現れるようになってから“それ”が何も口にしていなかったということに思い当たり、今まで何故そのことに気づけなかったのかという大きな後悔の気持ちと、“それ”が何を好んで食べるのか全く想像できなかったのでとにかくおなかいっぱい食べて欲しい、おいしいと思って欲しいという気持ちで泣きそうになりながら卵を溶き、チキンライスを炒め、オムライスを作りました。
幸い、その日の夕食に作ったカレーが余っていましたから温め直してオムライスにかけてあげました。
できあがったカレーオムライスを、冷蔵庫から這い出し私の足元でちゃっかりとあぐらをかいている“それ”に差し出すと、勢いよくスプーンで口にかき込んでいき、そして、息をつまらせそうになりながら、
「ふほっ、おいしい」
と言ったのです。
「ふほっ、おいしい」
食べながらしきりにおいしいと言ってくれるその様子があまりにもノブオに似ていて私は思わず鼻の奥がツンとしてきました。
“それ”の傍に座り、オムライスをかき込む姿を眺めているだけで愛おしい気持ちでいっぱいで息がつまりそうでした。
食事を終えた“それ”は皿を床に置き、今度は私の膝に這い上がってきました。
初めて触れる“それ”は想像していたよりはるかに暖かく、心地よいものでした。
“それ”が私に預けてくれる重さと同じくらいの重さを、私も預けることができました。
押しつ押し返され、ふたりゆったりと静かに深海へ降りてゆくようでした。
この感覚をどうして忘れていたのか不思議に思うほど、自然で、懐かしいものでした。
忘れてしまったとしてもまた思い出せるように今、しっかりとこの感覚を覚えておこうと“それ”のおなかに腕をまわし顔を埋めてしまったので私が言った「ありがとう」はきっと聞こえなかったと思います。
私たちはその夜、冷蔵庫の前で布団にくるまり、抱き合うようにして眠りました。
カレーのにおいが残っていたせいかカレーオムライスを食べる夢を見ました。
朝、目覚めると“それ”が布団から這い出して冷蔵庫へと戻って行くところでした。
その後ろ姿を眺めていた時に、今度ノブオと2人で写真を撮ろうと思いつきました。
私の部屋に置かれている冷蔵庫には思い出の写真や気に入っているポストカード、チラシの切り抜き、ステッカー、さまざまなものが貼られています。
一緒に撮った写真は、そう、これです。
彼は写真に撮られるのが好きでないのでまだこれ1枚だけです。
冷蔵庫っていうのは・・・毎日見る場所だから貼るんです。
それらの存在の大きさをいつも忘れないように。
それらを好きと思う気持ちを忘れずに作った料理を自分でも食べたいですし、大切な人に味わってもらうために。
今度ノブオにもカレーオムライスを作ってあげようと思っています。
これからはほとんど一緒に過ごすことになるから、いつでも作れるんですけど。
“それ”ですか?
今でもほんの時たま、忘れた頃にやってきます。
本当に時々です。